東京にとっては脅威とも見られがちな「ふるさと納税」。この制度には、▽地域支援の手段▽納税意識の向上▽自治体間競争の促進――の3つの意義がある。今回は地方自治の観点で、これらの意義について考えてみたい。
まず「地域支援の手段」とは、寄付によりその地域の環境や産業を育むというものだ。故郷や今までゆかりのあった自治体への応援の意味を込めた寄付はこれに該当する。
次の「納税意識の向上」は、寄付先を選ぶことで、納税者が税の使途を考える契機になる、というものだ。自治体の基本的な行政サービスに不満があるわけではなく、所得に応じた税負担が相互扶助の役割を果たし、住民間の格差を緩和することも理解している。ただ、そうした住民でも、自分の支払う税金の使途を改めて意識できることの意義は小さくない。
地方行政を「執行」と「経営」という役割に分けて考えると理解しやすい。行政事務や行政サービスを直接担う役割を「執行者」、権限が及ぶ地域全体のあり方を決める役割を「経営者」と見立てるのだ。
住民が自治体に対して影響力を行使する一つの方法が選挙だ。執行者に対する住民の関心事は「行政サービスをいかに提供してもらえるか」であり、その観点で候補者に投票する。ところが行政サービスの多くは法律に定められた事務であり、大きな差は生じにくい。もちろん細かな差異はあるのだが、それらは執行時にどの分野を重点的に行うのか、自治体の経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報)をどのように振り当てていくのか、どのような自治体を目指すのかという「政策」の問題、つまり経営者の役割と言い換えることができる。
本来、選挙では、候補者の政策が有権者の考えに近いか、さらに近い政策を示す候補者の中から最も執行能力がありそうな者を選ぶことが、民意を反映する道筋となる。ところが、地方行政では候補者間の政策の差異が際立つような選挙は行われにくい。より多くの支持を得ようと、包括的かつ抽象的な政策を示すことで、候補者の政策が中庸化していく傾向は政治学の研究からも度々指摘されているところだ。すなわち、執行者としての役割に多くを求めることができず、さらに政策に関しても中庸化以外の選択肢が与えられないのであれば、住民の地方行政に対する関心そのものが次第に失われるか、あるいは残された選択肢として「税金の使途」を意識する行為が際立つのは当然の帰結であろう。
住民の新たな意思表示手段
この状況を踏まえ、ふるさと納税の3番目の意義、「自治体間競争の促進」について考えてみよう。これは自治体が寄付者から「選ばれる」に相応しい地域のあり方を考え、それぞれの政策をアピールして競争を促すというものである。
住民がその地域に居住し続ける理由は、主に地縁や就業にある。そのため、政策に不満を抱えていても転居するまでには至らない住民も存在する。ならば基本的な政策は受容する一方、寄付という形で住民税の一部分を別の自治体へ移転することは、選挙に代わる一つの住民の意思表示手段になり得るのではないだろうか。
確かに税が流出する側の自治体は厳しい。平成27年寄付金税額控除の適用状況によると、東京都から流出する税額は約48億円に達している。一自治体当たりの減収額にしても数億円規模になり、行政サービスの低下を危ぶむ声もある。
自治体の経営現場に関わる身としてそうした懸念は十分理解できるが、それでも「減収をあれこれ嘆くよりも政策で勝負してほしい」という、一納税者としての思いには変わりがない。事実、私はある自治体の政策を評価しているので、そこにも寄付(ふるさと納税)をしている。政策への評価が財政という形でダイレクトに反映される点で、この制度は行政経営に対する新たな緊張感をもたらし、結果的には地方自治を良い方向に進めるものではないかと期待している。
このような状況下で自治体が寄付を受けるためには、他の自治体と政策上の違い(差異化)をアピールしなければならない。新たに施策を追加して差異化するのでは、経営資源がいくらあっても足りない。したがって、限られた経営資源の中で何を優先するのかを明確に示す必要がある。例えば、新たな施策を進めるために自分たちの裁量範囲を拡大するよう国に働き掛けるというならば、それは地方分権にもつながる。環境問題や新産業育成、災害復興といった具体的な施策を全面に押し出している自治体があるとして、ふるさと納税の仕組みなら、住民でなくとも寄付を通じてそうした政策に賛同・支持を示すことができるし、住民でも政策に賛同できない場合、他自治体への寄付でその意志を示すこともできるだろう。
国の想像を超えた考えを持つ自治体が政策の差異化を図っていくというのならば、賛同したい。その上で自治体の健全運営に資することを期待し、制度を活用すべきだと思う。
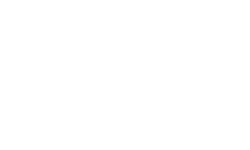 procureTech
procureTech

